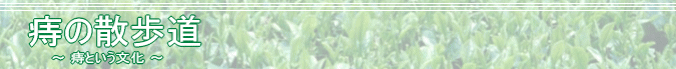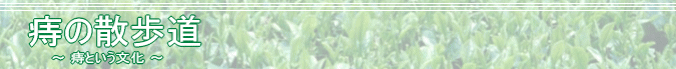| ~痔の治療に、蛭(ひる)を用いる!!~ |
人類は、古代エジプト時代から病気の治療に蛭(ひる)を用いてきた歴史があります。
我が国では、平安時代に編纂され現存する最古の医学全書である『医心方』の中に、脚病、癰疽、腫瘤(当時の病名)に生きた水蛭に毒血を吸わせる治療法が記されております。痔の治療法に蛭を用いることは記述されていませんが、江戸時代には、実際に使用されていた記録があります。
ところで、現代日本でも、医療用ヒルが使われているそうです。ヒルは、抗凝固物質ヒルディンを分泌し、再接着指や再建外科手術後の皮弁鬱血改善に有効であり。血管拡張作用、局所麻酔作用とともに、組織の微小血管の循環に寄与するとされています。
痔疾患では世界的に最も有名なナポレオンの痔の治療法として、主にヒルに血を吸わせたりしていたと伝わっていますが、日本での記録を見てみましょう。
江戸時代の文化文政期の漢学者である松崎慊堂(1771-1844)は、長年に亘る痔疾に苦み、彼の日記「慊堂日暦」に、痔痛や治療など関し、多くの記述があります。その中に、蛭を用いて治療した箇所があります。原文のまま一部引用します。
|
| |
■「慊堂日暦」より
|
天保三年五月一日
余はまさに治を廃し、温熨して旧套を守らんとす。而るに静海は云う、治はすでに半に及ぶ、ただこれを忍べば、全癒すること遠からじと。強いて再び蛭二十九頭を点じて咂わしむ。おわって少休すれば、咂口の血は淋漓としてやまず。哺後、熨薬を以てこれを熨すること半時、また水を灌ぐ。血止まる。道生は静海を助けて脱せるを収む。苦しみ言うべからず。半ば線牡を収め、痔痛は小滅す。膏薬を点じ、布半幅(長七尺)を以て腰骨を囲ること一匝、後余を以て軟膏上を過ぎ前布に係け、前余を以て交骨上に相結ぶ。昏、静海去る。一睡すれば疼処の白液は婦人の帯下の如し。布もて拭い、また睡る。近日、この況あることなし。
天保三年五月十八日
静海来り痔疾を診して云う、老血すでに竭く、蛭を上すを用いずと。ただ、綿を以て蜜陀を浸し、これを擁するに辺膏を以てす。春水来り、浴湯のことを語る。
天保六年五月四日
静海来り、痔疾を診す。蛭をつけて血を咂わしむ。凡そ五頭、血は五勺ばかりと云う。
参考文献:
日本口腔外科学会雑誌「遊離皮弁の鬱血に対するmedical leech(医療用ヒル)の有効性に関する臨床的検討」 Dec.2020
藤原書店『医心方』事始 槙佐知子著
文春文庫「ナポレオン・ミステリー」 倉田保雄著
平凡社「東洋文庫169 慊堂日暦〔全6巻〕」 山田琢訳注
上記引用文は、一部原文表記と異なる部分があります。
|
| |
|