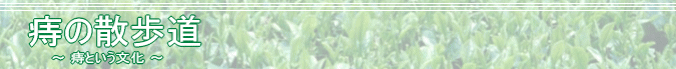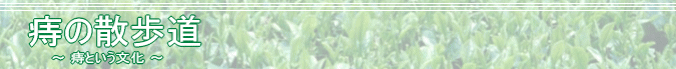岩川 隆(いわかわ・たかし)
1933年、山口県徳山市に生まれる。広島大学文学部独文科卒業。
著書『神を信ぜず-BC級戦犯の墓碑銘』(立風書房、中公文庫)、『多くを語らず』(中央公論社)、『海峡』(文藝春秋)、『キミは長島を見たか』(立風書房、集英社文庫)、『巨魁=岸信介研究』(徳間文庫)、『決定的瞬間』(中公文庫)、『競馬人間学』(立風書房、中公文庫)、『殺人全書』(光文社文庫)、『上着をぬいだ天皇』(角川文庫)、『どうしやうもない私』(講談社)など、小説からノンフィクションのジャンルに至るまで多岐にわたっている。
(岩川隆著「死体の食卓」悠思社 1991年11月20日 奥付から引用)
怪奇ユーモア小説集「死体の食卓」の第六話に痔鎮祭が収められています。
主人公である痔主サラリーマンの恋の物語です。
結末がわからないように、一部を引用させていただきます。
■第六話 痔鎮祭
(略)
他人にはあまり言えないことだが、痛みがしだいに遠ざかってゆくときの感覚は、痔主だけわかる恍惚境であった。敵は尻尾をまいて戦線を縮小してゆく。文鎮を吊りさげていたような尻の重力が消え、ふわふわと浮きあがる気分である。
(略)
「いぼ痔がなんだい。それくらいで驚くんじゃないよ。わしなんぞは、軍隊仕込みだぞ。北支派遣部隊の一兵として雪また雪のなかを行軍したあげくにできあがった痔だ」
(略)
「まあ、聞けよ。社内の人間がわしのことを交際の悪い男だと陰口をたたいていることも知っている。しかし、じつを言うと、わしは痔に苦しめられて酒も煙草もやめる羽目に陥った・・・・・・痔については、そこらの痔主とは桁のちがう苦労人だ。歩きようひとつ見ても、どの程度の痔かすぐにわかるんだ。」
(略)
「われわれ痔主のあいだでは、自らの尻と肛門の存在を忘れよ、という座右銘があってね。じくじくと肛門について思い患っていると症状が出てくる。ますますひどくなる。尻に血がさがるというのかなあ」
(略)
「同じような例がたくさんあるんだよ」
課長は痔薬専門メーカーの社員についてのエピソードを披露しはじめた。その会社の社員は症状の差こそあれ、すべて痔主になっているという。
「入社したときは肛門に異常がなくても、お客に対して連日のように症状を説明し、いかに肛門病の薬を売り込もうかと考え詰めるから、半年もしないうちに尻のあたりがおかしくなってくるそうだ」
(略)
(略)寝床に入ってから二十分から三十分もすると痒さは倍加し、蒸しタオルを肛門にあてたまま朝方までとんとんと叩き通す夜も出てきた。ありとあらゆる民間療法もこころみた。父がおこなっていた黒砂糖漬けのナメクジも患部にあててみた。ヒルも試した。ホウサンを洗面器にたたえて尻をひたすこともおこなった。だが、もっとも簡便な鎮撫法は無花果の葉をひたしたお湯に尻をつけっ放しにする方法であった。
「無花果はいいね。釣りは鮒にはじまって鮒に終るというが、肛門は無花果にはじまって無花果に終るよ」
(略)
「女房には内緒だが、あのA感覚の快感は、痔主でなければわからぬたのしみですよ」
(略)
〝し〝に濁点をふった〝じ〝という文字にはなんの刺激も感じない。しかし、〝ち〝に濁点をおくった〝ぢ〝の文字は、遠くからでも視界のなかにとび込んできて、肛門を思い出させる。〝ぢ〝は血であり、濁点はいかにも滴る血点のようで、ご丁寧にも〝ち〝の円弧を描くあたりは現実の臀部を連想させるようにふっくらと円味を帯びて書かれていた。
(岩川隆著「死体の食卓─怪奇ユーモア小説─」悠思社 1991年11月20日発行 から引用)
原文表記と異なる部分があります。
|