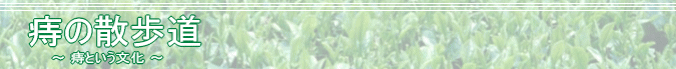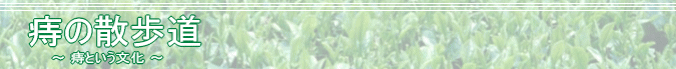「男と並んで愛誓うより、女と並んで笑いを取る、それが二人のしあわせなのだ! 駆け出しの漫才コンビ、『アカコとヒトミ』。超貧乏で彼氏なし、初ライブは全く受けずに大失敗。おまけにセクハラ野郎の先輩芸人を殴り倒して大目玉。今はぜんぜんさえないけれど、いつかはきっと大舞台。体に浴びます大爆笑――。夢と笑いとパワーあふれる傑作青春小説。第16回小説すばる新人賞受賞作。」
集英社文庫「笑う招き猫」 山本幸久著 2006年1月25日第1刷 カバーから引用
[著者]山本幸久
「一九六六年、東京都八王子市生まれ。中央大学文学部史学科卒業。『笑う招き猫』で小説すばる新人賞を受賞し、作家デビューする。著書に『はなうた日和』「凸凹デイズ』『幸福ロケット』がある。」
同上 集英社文庫「笑う招き猫」 山本幸久著 2006年1月25日第1刷 カバーから引用
■笑う招き猫
「痔」と書かれている箇所を中心に抜粋します。
(略)
ヒトミはもともとアイドルといったものに興味がないので、ふうんと気乗りしない返事をするばかりだった。しばらくして社長と呼ばれる人が入ってきた。アカコと変わらぬ小ささのその男は、地味な色の背広だったが、真っ当な職の人間には見えなかった。思わずヒトミは彼の両手に目がいってしまった。いずれの手も指は五本、健在だった。
部屋にあったパイプ椅子を二つ、中央に持ってきて、永吉は社長にひとつすすめた。ところが社長は、痔が悪化しちゃってね、とそれを断った。永吉としては、自分だけ座るわけにはいかないようだった。椅子を脇に置いた。彼も立っていることにしたらしい。
(略)
「ここはひとつ、俺を助けると思ってだよ。な」
仕切りのパーテーションは、とても低い。背の高いヒトミの胸のあたりまでしかない。そろそろと歩いていくと、やがてそのパーテーション越しに、社長の赤ら顔が見えてきた。彼は立って、しゃべっていた。どうしてだろうと思ったが、そうか、まだ痔が治っていないんだとヒトミは気づいた。熱弁している彼の相手は、ソファの向きのせいでこちらに背を向けているので、誰だかわからなかった。
(略)
「ちっこいほうか。殴ったのは」
「はあ」
社長はヒトミを応接室に招き入れ、ソファに座るよう、手で指図した。
ヒトミが腰かけても社長は座ろうとしなかった。
「痔が悪化しちゃってな。こんな柔らかなソファでも、腰掛けると痛くてたまんねえんだ。立ったまんまで失礼するよ」
(略)
アカコはリュックサックから、なにやら取り出して、テーブルの上に置いた。
「社長、そう言えば、痔」
「ああ、なかなか時間ができなくて手術にもいけねえんだよ。ソファに座っても痛くてたまんねえからよ。こうして突っ立ってるわけ」
「いや、それでしたらね、これ、うちの祖母が使ってるのと同じ薬なんですがね。なかなか効果あるらしいんですよ。どうぞ、差し上げます」
(略)
会社を出てからすぐに、ヒトミはアカコに突っかかった。
「あんた、まったく調子いいよね」
「処世術に長けてるって言ってほしいね」
「昨日はあたしのこと、へいこらし過ぎって言ったくせに」
「それはつまんない奴らにへいこらし過ぎってこと。あの痔持ちのちっこいおじさんは仮にも社長さんだよ。ちょっとでも好印象、もってもらったほうがいいじゃない」
「うちの祖母がって言っていたけど、頼子さん、痔だったっけ?」
「ううん。違うけど。あれはなんつうかなあ、リップサービス?」
言葉の使い方が間違っているような気がしたが、それには突っ込まなかった。
「誰かが使って効果があったなんて言ったりすると、ちょっと効き目ありそうじゃん。なんか手みやげあったほうがいいなと思って、家ん中、物色してたらでてきたんだ。誰が使ってたんだろ?」
「そんなの渡して大丈夫なの。使って痔が悪化したりしたらどうすんの」
はは、どうしようかねとアカコは笑うばかりだった。
(略)
「誰だよ、頼子さんって」
「彼女のお祖母さんですよ」
しばらくの沈黙のあと、「ああ、痔だった祖母さんか」と言ったので、ヒトミはおもわず噴き出してしまった。
(略)
同上 集英社文庫「笑う招き猫」 山本幸久著 2006年1月25日第1刷から引用
|