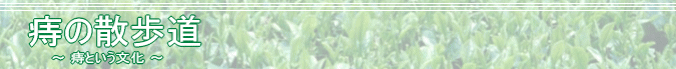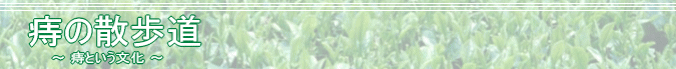大学病院の講師だった外科医、直江はなぜか栄進の道を捨てて個人病院の医師となった。優秀な腕をもちながらニヒルな影のある彼に、看護婦倫子は惹かれてゆく。彼の周囲には、さらに院長の娘や夫人らが群れ、慕い寄る。酒に酔い女に溺れながらどこか冷めた直江には、ある秘密が隠されていた・・・・・・。
話題のテレビドラマ「白い影」の原作として、医学界の内幕をも抉り、反響を呼んだベストセラー。作者の力量を十分に物語る傑作長編小説。
角川文庫「無影燈《むえいとう》 (上) (下)」全二冊 渡辺淳一《わたなべじゆんいち》著 平成十四年一月二十日 改版七十五刷発行 のカバーから引用
[著者]渡辺淳一
一九三三年北海道生まれ。札幌医科大卒。一九七〇年『光と影』で第六十三回直木賞。一九八〇年『長崎ロシア遊女館』と『遠き落日』で第十四回吉川英治文学賞を受賞。美しい日本情緒の中で息づく男女の愛と性を鋭く描出した作品。明治時代を中心とした歴史的伝記的作品など幅広く活躍。主な著書に『静寂の声』『化粧』『浮島』『ひとひらの雪』『うたかた』など多数。
同上 「無影燈(上)」の カバーから引用
■無影燈
「痔」と書かれている箇所を中心に抜粋します。
(略)
婦人科の亜希子の声で、純子は診察台に上がった。黒いレザーの敷いた台へ、手をついて上がると、仰向《あおむ》けになった。
「もう少し体を前に出して」
言われるとおり純子は下半身を台の端へ押し出すと、自分から股を開いた。純子の肌は白というより、蒼に近かった。
(略)
「あたし痔もあるんだけれど、ついでに診てもらおうかしら」
(略)
時計表示法でいう三時と六時の個所に、はっきり閉痔核とわかる大きなしこりがあった。頂点は充血し一部は糜爛して破れたばかりらしく、ゴムの指先に血がついてきた。八時の位置には肛門の粘膜の皺壁が釣り鐘状にとび出し、外痔核もできていた。愛らしいお臀からは想像もつかぬ進んだ病状だった。
(略)
「手術をしなければ駄目ですか?」
「いかんね」
「でも随分日数がかかるんでしょう」
「根治手術をするとなると一か月は必要だ」
「もっと簡単にやる方法はないんですか」
純子はベッドに起き上がって、ネグリジェの裾を下した。
「痔核をとるだけの手術ならそんなにかからないが」
「半月くらい?」
「まあ、そんなところだ」
「やってしまおうかしら」
「これではたしかに可哀想だ」
「ひどい時は大きな声を出しただけでも響くのよ」
「時々出血するんだろう」
「そうなんです」
「君の顔色が蒼白くて貧血なのは痔の故だったのだな」
「困ったわ」
(略)
直江の言葉にマネジャーはうなずいたが、その眼はなお、不安そうであった。
「それより、花城君の痔はかなり悪いですよ」
「昨夜、花城から聞きましたが、やはりいけませんか」
(略)
マネジャーは太い膝を貧乏揺すりのように動かした。
「もう少し簡単な手術はないものですか」
「痔核をとるだけという手術もあるが、それでは完全な治療とはいい難い」
「それでも治ることは治るのですね」
「一時的には」
(略)
マネジャーは天井へ眼を向けた。
「この際、一気に痔の手術をやってしまうということはどうでしょうか」
「やってやれないわけではないが」
(略)
「彼女どうなの、まだパパの病院にいるんでしょう」
「あっちの方は一応納まったが、今度は痔の手術をするんだ」
「そんな病気もあるの?」
「言っちゃいかんぞ、この前うちの若い医者が口を滑らして大変なことになったのだから」
「言わないわ、パパのことだって誰にも言わないでしょう」
「当たり前だ」
「痔なんて嫌あねえ、誰が手術するの?」
「やはり直江先生だ」
(略)
ここまで、「無影燈(上」)、以下「無影燈(下)」
(略)
一日一万五千円の病室を占領しているのは、いまは花城純子一人であった。
彼女は十二月に入ってすぐ痔の手術を受けた。
直江はホワイトヘッド氏法という根治手術をすすめたが、年末の歌謡番組のスケジュールは外せないということで、結局手術としては最も簡単な痔核摘出術だけにとどめた。
(略)
「それが子供を堕したり、痔の手術をしたり・・・・・・」
「彼女は清純という演技をしているだけですよ」
(略)
「一晩つき合って下さい。一緒に飲みましょう」
「先生はお忙しいし、お酒は痔に一番いけないのよ」
冷えた声で倫子が言った。
(以下略)
同上 「無影燈)(上)(下)」から引用
原文表記とは一部異なります。
|