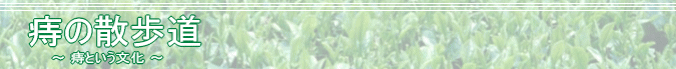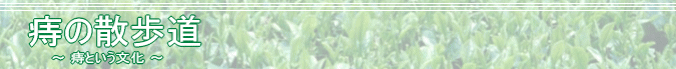■『遠き落日』(渡辺淳一著)
野口英世の伝記小説 〜痔になってお金のないことに気がつく〜
渡辺淳一(1933―2014年)の作品は、整形外科医師の経験を踏まえた「医学小説」をはじめ、「恋愛小説」、「伝記小説」、「エッセイ」など多岐に及んでいますが、特に『失楽園』や『鈍感力』が有名です。
その膨大な著作のうち、三つの小説(『遠き落日』、『静寂の声』、『無影燈』と一つの随筆『新釈・びょうき事典』に、「痔」が描かれています。
ここでは、『遠き落日』を紹介します。「痔」と書かれている箇所を下記に抜粋します。
■『遠き落日』の概要
一九一九年、メキシコの街メリダで野口英世の黄熱病に関する講演を聞いた人物がいる。ドクター・オトリイオ・ヴィラヌエヴァである。この人物に会いに行くところから、作者の野口英世をめぐる旅が始まった。
野口英世の生家は祖父母の代からの貧農だった。一家の生計は母親の血のにじむような働きに支えられていた。母親は自分の不注意から障害をもたせてしまったため、野口英世を溺愛する。
経済的に恵まれない人間が細菌学の勉強をつづけるためには、強引ともいえる処世術と、何を言われても気にしない図太い神経を必要とした。野口英世はそうした強烈なエゴイズムの持主でもあった。
研究面でも野口英世のやり方は唯我独尊的だったが、着々と成果はあがって、栄光の階段を昇っていく。世界では認められても、日本では認められないことが不満だった野口英世は、黄熱病の研究に没頭する。エクアドルに渡り、わずか三ヶ月で病原菌を発見。しかしこの発表も強い不信の目で見られてしまう。
そこで五二歳の野口英世は、自説を証明するため、みずから開発したワクチンを注射してアフリカへ乗りこみ、その病気研究中に没した。その後の研究で、黄熱病の病原体は菌ではなく、光学顕微鏡などでは見ることのできないウイルスであることがわかった。
その死をもって黄熱病の存在を証明しようとした野口英世の生涯は、先駆者の悲劇といえよう。作者はその赤裸々な人間像を刻むことで、野口英世神話に挑戦し、虚飾を剥いだ、人間、野口英世の姿を現代に蘇らせた。
一部原文表記と異なる箇所があります。
集英社「渡辺淳一のすべて」 編者『渡辺淳一恋愛小説セレクション』編集室
二〇一八年六月三〇日発行
■「痔」という言葉が書かれている箇所を抜粋
(略)
日本人ならいざ知らず、外人に借りた金は払わないわけにはいかない。とくにマドセンやファミュルナーは学問上の師であり、友である。「漫遊の借金」というのは内容はともかく、事実ではあった。
だが借金に慣れていた英世も、さすがにこの年の冬には、自分の金銭への計画性のなさに自分であきれ、これでは駄目だと改めようとした。
そのきっかけになったのは、この年の秋から冬にかけて悩まされた痔疾である。もともと英世には痔の気があったが、長年の椅子への坐りづめと、この冬の寒さによって一気に悪化してきた。下宿から研究所へ十分とかからぬ道を歩くのさえ辛く、そろそろと歩幅を縮めながら行くので倍以上の時間がかかる。
医師に診てもらうと即座に入院して手術を受けなければならないという。迷った末、痛みに耐えかねて決心したとき、初めて金がないのに気がついた。保険制度のまだ完備していなかった当時のアメリカでは、手術を受けるとなるとかなりの出費になる。
(略)
一部原文表記と異なる箇所があります。
角川書店 渡辺淳一全集 第7巻 「遠き落日 他四編」平成八年三月二十七日発行
から引用
|