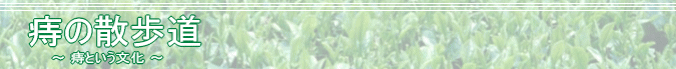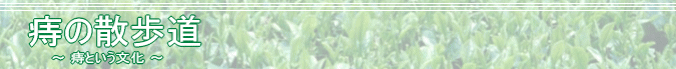阿川弘之
1920(大正9)年、広島市生れ。‘42(昭和17)年、東大国文科を繰上げ卒業し、海軍予備学生として海軍に入る。戦後、志賀直哉の知遇を得て師事。’53年、学徒兵体験に基づく『春の城』で読売文学賞を受賞。同世代の戦死者に対する共感と鎮魂あふれる作品も多い。芸術院会員。主な作品に『雲の墓標』『舷燈』『暗い波濤』『志賀直哉』のほか、『山本五十六』『米内光政』『井上成美』の海軍提督三部作がある。
(「食味風々録(しょくみぶうぶうろく)」阿川弘之著 新潮文庫 カバーから引用)
■「あくび指南書」 第1回「粗忽の使者」から
恐怖は感染するが痛みは感染しない。人の痛いのなら三年でも我慢出来る。
「大丈夫だよ、君。人間、歯痛で死にゃしませんよ」
痛い痛いと大袈裟に騒ぐな、痛けりゃ早く歯医者へ行けばいいんじゃないかと思っている。
―それが、一旦自分のこととなったら片時も我慢できない。
「痛い痛い、痛い」
「イタイイタイ、いたいいたいいたい」
何がさほどに痛いかというと、尾籠ながらお尻が痛い。
三十余年前、落し紙にも不自由していた敗戦直後、この病に取りつかれ、一度、注射だけで治すと称する怪しげな医者にかかって手術(?)を受けたが、日ならずして再発した。
お前、馬鹿だ」
と引揚者の兄に言われた。
「手術なんかするから再発する。俺も長年の痔持ちだが、医者には見せん。手術もせん。したがって再発しない」
以来、家兄の教えに従って医者の門を叩かず、だましだましてこんにちに至っている。兄は十年前心臓の発作で急逝し、しもの宿痾と永別した。私の場合も、長くてあと二十年か二十五年ごまかしつづけていれば、大概こいつと縁切れになるだろう。
ただ、そこまでの道程において、時々木曽の御岳さんみたいなことが起るのが困る。これから新しい仕事にかかろうという時、尻の噴火が始まってまことに困惑している。
妻子は別室で安らかに睡眠中。何たる無慈悲無神経な家族かと恨めしい気がするけれど、起してみたところで痛みが和らぐわけではない。
(略)
(あと少し、おもしろい痔談義は続きますが、引用は控えることにします。)
(「あくび指南書」阿川弘之著 毎日新聞社 1981年4月15日から引用)
一部原文表記と異なるところがあります。 |