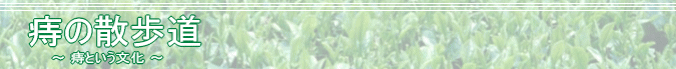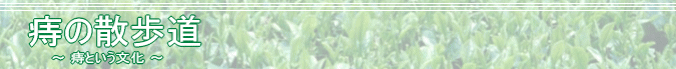■イカは痔の薬
むかし、上州から越後へ旅した男があったとさ。
むかしは田舎には宿屋などなかったから、親切そうな家をみつけて泊めてもらったと。
男が寝ていると、となりの部屋で、なにやらひそひそ話す声が聞こえてくる。
「今夜はなにもできなかったから、明日は半殺しにすべェかのォ。それとも、手打ちがいいかのォ」
男はびっくりしてとび起きた。
「えらい家に泊まってしまった。半殺しにされても、手打ちにされてもかなわん。すきをみて逃げ出すべェ」
夜中すぎ、家中が寝しずまるのを待って、男はそっと部屋から出ていった。
囲炉裏のおきで、あたりがぼんやりと見える。目をこらすと、囲炉裏っぱたにうまそうなイカが置いてあったと。
「明日はなんにも食えんかもしれない。これでもごちそうになっておくか」
男は、囲炉裏の火でイカをあぶるとみんな食ってしまったと。
イカを焼くにおいで目をさましたのか、だれかが起きてくるけはいだ。
「しまった。逃げそこねた」
男はあわててもといた部屋へとびこんだと。
そのまま、夜があけてしまったので、男はおそるおそる出ていった。
すると、囲炉裏っぱたにいたじいさまがいったと。
「お客さん、よく寝られたかね。まあ、ここへきて、ぶちたたかっしゃい」
男がきょろきょろしていると、じいさまが、また、いうんだと。
「ぶちたたかっしゃい。ぶちたたかっしゃい。」
そこで男は、寝ていた猫をおもいっきりひっぱたいたと。
「お客さん、なんで猫をたたくんだね」
「じいさまが、ぶちたたかっしゃいって、いったじゃないか。おれんとこでは、猫のことをぶちっていうから、猫をひっぱたいたんだ」
「そうかね。わしは、いろりで焼いてる焼きもちの灰を囲炉裏ぶちでたたいて食べろっていったつもりだったんだがね」
そこへ、この家のばあさまが起きてきた。
「夕べ、ここへ置いといたイカを知らないかね」
「わしは知らねえな」
じいさまがいったと。
「へんだねえ。たしかに置いといたんだけどねェ」
ばあさまがあんまりいうんで、男ははくじょうしたとさ。
「じつは、夜中に腹がへって、ここにあったイカをごちそうになりました」
「あれ、食べちまったのかい。お客さん、どうすべェ」
「どうしたんでしょう」
「じつは、あれは痔の薬で、昼間はおしりにおっつけておくんだけれども、夜はじゃまなんでここへ 置いといたんだ。お客さん、食べちまったのかね」
男が目をしろくろさせていると、おかみさんが山のようにぼたもちをこさえてもってきた。
「さあ、半殺しだよ。いっぱい食べとくれ」
「これが半殺しですか」
「そうさ。うまいよ」
「それじゃあ、手打ちっていうのはなんですか」
「手打ちっていうのはうどんさ」
「なあんだ。わたしは殺されるのかと思った」
安心した男は、ぼたもちをいっぱいごちそうになって、でかけていったとさ。
あかぎ出版 「ふるさとの民話 高崎」 監修 木暮正夫 著者 後藤博子・高井恵子 発行日 一九九〇年十一月二十四日 から引用
|