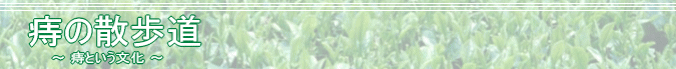
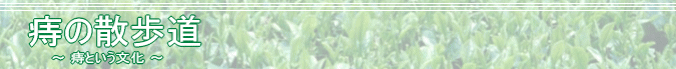
| ■大だわけ痔持牛蒡を焼いて付け (樽一三一25) ■はさみけり・痔の妙薬ハなすひつけ (明二・仁6) ■ 「という句である。さて、これはどんな放屁であろうか。当時、布地を断ち切る際には、切り口を付けて、鋏を用いず手で一直線び裂く事が多く行われた。普通の布地などは少し甲高い音を発して、ぴぴーと一気に裂ける。黒縮緬の場合は、縦糸と横糸の関係から一気には裂け難く、鈍い音を発して中々切れないのであろう。痔持ちの屁は、痛みが伴うために、少しずつガスを発して静かに静かに長々と放出する。一気に破裂的にはいかない。これはあくまでも、筆者の想像的解釈である。読者の方々の豊な空想にお任せしたい。(「江戸のおトイレ」渡辺信一郎著 新潮社) (新一8) ■御痔疾へ曾呂利牛蒡をやいてつけ 「『猿の尻はまっかっか牛房焼いておっつけろ』とうい俚謡に因んでの句か。」(川柳江戸の民間療法」小野眞孝著) (樽三九3) ■後架から扨なんざんと痔持出る 「やっと排泄を終えてトイレから出て来た痔病みの男(女?)、痛みを堪えながら成し遂げた行為に安堵感を覚え、「さても、さても難産であった」と述べている情景である。女が遭遇する困難な出産に仮託している所が、面白い。「難産」の第二義として、「物事がたやすく成就しないこと」の意もあるが、排出する苦労を洒落ていて、秀逸な句となっている。「難産、色に懲りず」(苦しいめにあっても、性懲りもなく同じ行為を繰り返す)という俚言があるが、このイメージを背景として置いているとも考えられる。」(「江戸のおトイレ」渡辺信一郎著 新潮社) (安元義6) ■晒六尺痔の神とて書き上げ 「幟。褌も晒の六尺を用いる。」(小野眞考著「川柳江戸の民間療法」から) 痔の神秋山自雲に願を掛け、治ったお礼に幟を奉納する寺もある。痔の神には、幟も褌か。 (樽一〇四13) ■痔を見てせざるはいさみ無和尚也 (又は 「和尚が、男娼と肛交かまたは寺小姓とのそれの場面である。後庭華を提供するのを常とする者は、痔疾に罹ることが多いと言われる。排泄器官である肛門を、無理に逆方向から開かせるために、肛門周辺や直腸を損傷するのである。練習を究め、潤滑剤を使用しても、女陰の膣の筋肉組織とは異なり、その伸縮性においては格段に劣るものである。狂歌集『六樹園家集』雑の部(天明七頃−一七八七)に、 さしあたり何とせん つつがなく守りてたまへ痔の神よあはれとしりの穴のあたりは 陰間述懐とあり、往々にしてこんな事もあったという証である。 と言う言葉があって、これは『人として当然なさねばならぬ事と知りながらしないのは、真の勇気がないのである』という意に解されている。この文句を巧みに使って、それをパロディー化しただけの句である。(略)」 (「江戸破礼句 梅の寶匣」 蕣露庵主人著 三樹書房) ■痔をもった仏達磨の支配うけ (樽一一五8) ■ぢになるは承知和尚と小性の碁 (樽1177、一一七19・28) ■ 「弘法大師は男色の祖だと。」(「川柳江戸の民間療法」) 「弘法大師が男色の道を開いた始祖だとすれば、痔の治癒を祈願する神仏も、この弘法大師だと思い込んでいる陰間の気持ちを言う。」(「江戸の色道-古川柳から覗く男色の世界」渡辺信一郎著新潮社) (天七・十・二五) ■痔の医者は諸人の尻で飯を喰ひ 「『咄し家は世間ンのあらで飯喰イ』(一〇〇・128)という句もあるが、口ならぬ尻で飯を喰うというくすぐり。」(小野眞孝著「江戸の町医者〈新潮選書〉」 (樽一〇〇150) ■痔の神へお七何だか願をかけ 八百屋お七の恋人は、寺小姓だった。お寺は男色が盛んなため、あのお七も恋人を案じて願をかけるというもの (樽一六五10) ■痔の願にお七はこんきくたく也 「根気を砕くは色々と心を痛めること。八百屋お七が恋人である吉三郎の身を案じて。」(「川柳江戸の民間療法」) (露丸 明三・貞1) ■痔の神へ左ねじりの初穂銭 「賽銭を包んだ紙を左ねじりに。糞のことを左ねじりというのにかけての句。」(「川柳江戸の民間療法」) 「当時も痔疾を患う人々が多くいて、最後の手だてとして病の快方を祈願して、霊験あらたかな神社へお参りした。江戸の各地に、痔の神様が存在し、噂が噂を呼んで参詣者で賑わった所もある。「初穂」は、その年初めて収穫した穀物などを、神仏へ奉納する事である。その習慣から、穀物の代わりに金銭を奉るのが、「初穂銭」である。当時の庶民たちは、お賽銭十二文を懐紙に捻り包んで奉納するが、痔の神様だけに縁のあるように「左捻じり」にする状況を言う。(「江戸のおトイレ」渡辺信一郎著 新潮社) (樽一二九20・22) ■痔の神を売った祟で尻を抱 痔の神「秋山自雲」が祀られている「山谷本性寺へ詣るとの口実で(売って)近くの吉原へ。その罰で遊女にふられて尻を抱いて寝る破目に。」(「川柳江戸の民間療法」) (樽九八56、九十九94) ■一念を石にとゞめし痔の薬 山谷本性寺の秋山自雲の墓。江宝暦12黛山評(鈴木勝忠編著「続雑俳語辞典」明治書院) ■痔の神の加護をも頼む陰間茶屋 「商売物の陰間が痔にならぬようにと。」(「川柳江戸の民間療法」) (樽一三二28) ■痔の神の神木らしい児ざくら (樽一三一6) ■痔の神は神のうちでもいつち尻 「痔の神だから一番どん尻だ、と」(「川柳江戸の民間療法」) (樽七六36) ■痔の神は水道尻と知たふり (樽一四四3) ■痔の神はびろうながらの願をきヽ 「『尾篭ながら』と断りを入れて。」(「川柳江戸の民間療法」) (樽一一〇18) ■痔の灸に釜屋艾はいつちきヽ 「句の釜屋 「いっちきゝは一番よく効く。痔と釜(男色)の連想。」(「川柳江戸の民間療法」) (樽一二一乙15・45) ■痔仏へ願なをつたら尻くらひ 「 (樽七七26) ■痔仏をひたすら念ず寺小性 「痔仏は持仏のしゃれ。」(「川柳江戸の民間療法」) (樽一〇六16) ■痔持の大屋困つてるけつだん所 (樽一五〇30) ■痔持の生酔歩行てく千鳥穴 (樽一〇六39) ■痔持の盗人たれるうち夜があける (樽八二11、八三58) ■尻の病にかつぱを川へ捨 「河童は尻子玉を抜くといわれるが、河童の好物である胡瓜(かっぱ)を投げ入れる。」(「川柳江戸の民間療法」) (樽六六16) ■雪隠で蚊のいけにへに痔持なり 痔持ちは、便所が長いからか (樽一一一12・16) ■雪隠に治兵衛は尻をかヽへてる 「『治兵衛』は『痔兵衛』と同義である。排便をしながら、痛みや脱肛を気遣うので、尻を抱えるようにして蹲踞している状況である。」(「江戸のおトイレ」渡辺信一郎著 新潮社) (筥四11) ■相違あらざる痔疾の状湯冶 「痔疾と自筆。」(「川柳江戸の民間療法」) (樽一二四別44) ■底倉へ菊の療治に 「謡曲『菊慈童』のイメージである。紀元前、周の穆王に寵愛された小姓の菊慈童は、勘気を被り他郷に流され、菊の露を飲んで不老不死となったという伝説がある。穆王に寵愛されたということで、後庭華を提供したという認識と。『菊』が肛門の隠語であるから、男色に結び付けることが多い。そこで、底倉温泉へ『菊の療治』に痔を患った若衆が来るという意味になる。」(「江戸の色道-古川柳から覗く男色の世界」渡辺信一郎著新潮社) (樽一二〇25、一二八32) 痔の治療に温泉に行った。江戸時代最も有名なのが、箱根七湯のひとつである底倉温泉で、よく川柳にもうたわれている。 芳町とは、江戸時代に陰間茶屋があった場所で、その芳町の陰間が、痔の温泉療法のため底倉に来るということである。 次のような句がある。 ○底倉の ○底倉の ○底倉で見た芳町の美少年 (一二三別26) ○芳町の釜は箱根で ○底倉で ○京ことばに ○底倉は (この底倉に関する上記の川柳、狂歌は、すべて「江戸の色道-古川柳から覗く男色の世界」渡辺信一郎著 新潮社から引用) ※底倉温泉と箱根七湯については、本ホームページ「痔を癒す温泉」、「箱根七湯と七湯の枝折」でも紹介しています。 菊慈童に関しては、次のようなものもあります。 ○お ) 「 ■湯冶場で馴染お八重と痔兵衛さん 「おやえは黴毒の異称。花は鼻に通じ、八重梅の梅は黴に通ずるのでいうと『江戸語大辞典』にあり。痔兵衛も痔持ちの擬人名で、梅毒と痔の患者が湯冶場の馴染客である。」(「川柳江戸の民間療法」) (樽一四一18) ■長雪隠淋兵衛殿か痔平殿 (樽一一二23、一二三65、一二六60) ■難痔しらずや鍛冶丁の達磨をば 「神田は鍛冶町に、屋根つき看板の上に達磨を飾った薬屋があった。五宝円という家伝薬の店だが、本来は性病の薬。これを痔にも応用したのか。難痔は汝にかけたもの。」(鈴木昶著「江戸の医療風俗事典」) 「難痔と汝の掛け言葉。面壁九年に痔を通わしたものか。」(「川柳江戸の民間療法」) (樽一一八10) ■走り痔で 「という凄絶な写実的な句もある。「走り痔」は、出血を伴う痔であるとされるが、着物の『裏衿を出す』というのは、脱肛の様子を言う。褻《け》の世界を何とも凄い例えで描写している。 (樽一二九20・22) ■びんずるをもちあげて痔持撫る也 びんずるは、「賓頭廬」で不動の意の梵語の音訳。羅漢の一人。頭髪が白く、まゆが長い。その像を手でなでて祈ると病気が治るという。(新明解国語辞典) お寺の本堂などに置いてあります。 痔持は、持ち上げてお尻に触れないといけない。 (樽三六10) ■ひんずるをもちあげてなでる寺小性 (宝十三・礼4) ■芳町の仁者痔を見てせざる也 芳町は、陰間茶屋が多くあった。 (樽九六20) ■淋兵衛と痔兵衛どちらも長後架 「同想の『長雪隠淋兵衛か痔平殿・一二二23』という句もあり、淋病と痔疾は長雪隠の定番である事が知られている。(略)淋病の者は残尿感があるため、早く切り上げるのが困難であり、痔疾の者は痛みに堪えながら、静かに時間を掛けて排出するために、長雪隠となるようである。(「江戸のおトイレ」渡辺信一郎著 新潮社) (九大追福20) ■若殿の痔ははへぬきのやまいなり 「という川柳がある。 江戸時代には男色(男性の同性愛)が盛んであったようで、美貌のお (樽二1) ■女の痔まつたく前のひゞきなり (安九・桜3) ■わる堅い屎に痔持の儒者困り (樽一五二3) ■師の恩の身にしみじみと痔の痛み 「師匠から修行の手ほどきを受け、仏学も身に付くようになるのは、まさに師の恩であるが、肛門に受けた痔疾も「師の恩」の一端ということである。」(「江戸の色道-古川柳から覗く男色の世界」渡辺信一郎著新潮社) (一二一乙28) ■師の恩は今に忘れぬ痔の痛さ {少年の時からの修行の厳しさをしみじみと述懐すると、仏学の蓄積向上の辛さとともに、師匠から蒙った痔の痛みも、一入深く偲ばれるのである。」(「江戸の色道-古川柳から覗く男色の世界」渡辺信一郎著新潮社から引用) (一〇六9) ■お 「という、そのものずばりを言った句がある。寺の住職の要求通りに実践したところ、見事に住職の脚気は全快したが、そのため小僧は痔持ちになってしまったという現実である。」(「江戸の色道-古川柳から覗く男色の世界」渡辺信一郎著新潮社) (潘山瓦長両評・享保中期) ■色男ちっとかそっと痔持ち 「肛交をされ続けていると、痔疾に陥ることは常識であった。そこで、色男は男との肛交の経験者であるため、少しは痔の気があるという訳である。」(「江戸の色道-古川柳から覗く男色の世界」渡辺信一郎著新潮社) (明二桜4) 一部原本と異なる表記があります。 |
|||||