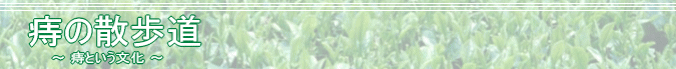
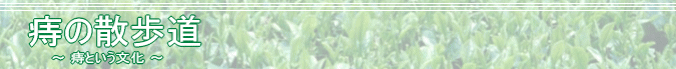
| ■ルイ14世■ 太陽王・ルイ14世の痔瘻 ここでは、三つの書籍からフランスの太陽王ルイ14世の痔ろうを紹介します。 「やんごとなき姫君たちのトイレ」、「お尻とその穴の文化史」、「ルイ14世の時代」から抜粋します。 それぞれ長い引用をします。 「お尻とその穴の文化史」については、著者がフランス人の医師であり、また、引用した資料も明らかにされており、王の痔瘻について、その症状、処置、手術内容などの経過が詳しく記載されています。 「やんごとなき姫君たちのトイレ」から 華麗なる太陽王の侍医 一七世紀のヴェルサイユに君臨した、太陽王ルイ一四世。この王の侍医ダカンは、妙な学説を主張していた。人間の歯は、あらゆる病気の感染の巣であり、一本でも歯があるかぎり、何かの病気に感染する恐れがあるというのだ。 おかげでダカンはルイ一四世の歯を、一本残らず引っこぬいてしまった。もちろん、良い歯も悪い歯も一緒くたである。 ルイ一四世はこの大抜歯を勇敢に耐えたが、さらにダカンは、王の下あごの歯とともにアゴまで砕き、上アゴの歯とともに、口蓋の大半を取りのぞいてしまった。これらの処置はすべて、麻酔なしに行われたのだ。 おかげで太陽王は、何十年ものあいだ歯なしの生活を強いられた。入れ歯などという便利なものはなかったので、食べ物は噛むことができず、飲み込むだけだ。当然、消化不良に悩まされる。 そこで、ルイ一四世は、毎日のように下剤を飲まされ、食べては下し、下しては食べの、悪循環をくりかえした。一日に一五回以上も便器に座ったという記録がある。便器の間にあわなくて、おもらしすることもしょっちゅうだった。 (略) またある日、太陽王のお尻に、 外科のオーソリティであるフェリックス教授は、一か月以上も、これら人間モルモットのお尻を縦横無尽に切りまくった。気高い王のお尻にメスを入れるには、このくらいの犠牲は、当然というわけである。 (略) かくていよいよ、ルイ一四世の痔の手術にとりかかることになった。これもなんと麻酔なしだから、それこそ死ぬほどの痛みだったろう。いかも手術の直後、王はいつもどおりミサに出席し、貴族たちの面前で昼食をとり、午後には椅子に座って何時間も国政会議を主宰したというから、恐ろしい。 (略) 「やんごとなき姫君たちのトイレ」桐生操著 角川書店 平成9年4月30日6版発行 (原文表記と異なる部分があります。) 「おしりとその穴の文化史」から 5・・・太陽王ルイ14世の痔瘻 (略) ルイ十四世は、その長い在位期間中に、慢性的疾患をくつも患っていて、日誌(ルイの歴代の侍医が書きつないだ『ルイ十四世の健康日誌』)の頁の大半はそのことについて書かれている。くり返し洗浄(灌腸ではない)する理由となっていた腸障害、頭の働きが鈍くなる毒気とめまい、そして痛風の発作である。ほかの病気は単に付随的なものにすぎない。一六八六年の大半と、一六八七年の初めにかけて、一年以上宮廷内の噂の中心となったあの悪名高い王の痔瘻も、そんな付随的な病気である。 「会陰近く、縫線の脇、アヌスから指二本分の幅のところにある小さな腫瘍」について、王が最初に訴えはじめたのは、一月十五日だった。当初は痛みも耐えられたが、炎症が急速に進行し、不快感は耐えがたいものとなった。 二月の初めに王は、セイヨウビラフジ、ライ麦、空豆、亜麻の実を砕いて粉にしたものを、酢水のなかで煮立ててつくったバップ剤を貼ることを受け入れた。しかし、その効果は、もっと伝統的な、鉛白やドクニンジンの膏薬や、ゴム、松ヤニ、オオバコ水を染み込ませたという、興味をそそられる「ゴルティエ布」ほどではなかった。 伝統的な薬物療法が失敗したので、いよいよ外科処置を施すことになる。「焼灼法のために焼いた大きな石を二つ、腫瘍にあてがった。すると (略) いちばんの当事者、つまり太陽王の同意を得て、あらためて手術することが決められた。フェリックス氏(外科医)が「先にメスをつけた特別あつらえのゾンデを、瘻に沿って腸にまで挿入したところで、ゾンデの先を腸内の右手の指で触ることができた。手を下へ引き抜き、今回はかなり容易に瘻を切開することができた」。次いで、傷口に挿入したハサミで腸と結合組織を切り開いた。こうしたことはすべて麻酔なし、生身のまま行われた。「王はあたうるかぎりの忍耐力でのり越えられた」。 そのときの癒合も速かった。もしかしたら『日誌』の記述では速すぎるかもしれない。「瘻の道筋にあるいぼ」にけりをつけるために、さらに三回の小さな手術が必要だった。しかし、一六八七年五月には、王はもう治ったと思うことができた。最初の腫瘍の兆候が現れてから一四カ月が経っていた。 (略) 「お尻とその穴の文化史」作品社発行 著者 ジャン・ゴルダン、オリヴィエ・マルティ 2003三年8月25日第1刷発行 (原文表記と異なる部分があります。) 「ルイ十四世の世紀(二)」から 第二七章 (略) 一六八六年病気になり、それが中々重かったのも手伝って、今まで、ほとんど毎年のように、趣向を変えては催された、いわゆる艶なる (略) ルイ一四世の体に、この病気の最初の兆候が現れると、外科の侍医の筆頭のフェリックスは、早速、方々の病院を廻って、同じ危険に陥っている患者を訪ねた。一流の外科医の意見を聞き、その協力を仰いで、手術の時間を短くし、かつ、苦痛を軽減するため、色々な器具を考案する。王は、苦痛を訴えることなく、手術を受けた。その日、すぐに、大臣たちを呼んで、寝台の側で、仕事をさせる。さらに、危険の知らせが、ヨーロッパ中の宮廷に、少しでも、異変を起こしてはというので、翌日になると、早速大使たちに接見するというありさま。この精神力は大したものだが、フェリックスの労を (略) 「ルイ一四世の世紀(二)」[全4冊] 岩波書店 ヴォルテール著 丸山熊雄訳 1984年6月20日 第5刷 (原文表記と異なる部分があります。) ■芥川龍之介 この文豪の痔は、大正10年30歳のとき、4か月に亘る中国への視察旅行からの帰国後に、胃腸障害(特に下痢)、神経衰弱とともに発症しています。この3つの病は、昭和2年芥川が自殺するまで、芥川の持病となります。 ただし、痔の程度としては、芥川の主治医で自殺直後に診察をした下島医師によれば、「これは脱肛として現れる種類のもので、寒い夜中の勉強が過ぎたり、或は気候の悪い時分に力作をしたりするときに起る。時々疼痛の劇しいため苦しむこともあるが、出血したり或はコンニヤクやバツプなどで温めて、安臥していれば充血が去って収縮する程度のもので、手術の必要ありなど認めらたことは一度もない。この起り始めは胃病と同時ころか、或は少し前であったか判然しない。」(「芥川龍之介の回想」から、なお、旧字体は改めています。)と診断しています。実際に、手術は行っておりません。痛みがあるときは、坐薬を用いたりしていたようです。 芥川の知人あての書簡にはこの痔に関する記述が散見され、また、小説「歯車」に痔の文字が記載されています。その一部を次に引用します。 ○書簡から 大正十年九月十三日、下島医師宛 「(略)この間の下痢以来痔というものを知り、恰も阿修羅百臀の刀刃一時に便門裂くが如き目にあひ居り候」と記し、そして同じ書簡の中で「秋風や尻ただれたる女郎蜘蛛」という句も詠んでいます。 大正十五年六月二十日、神崎清宛 「(略)君は好い日に来た。あの翌日以来腹を下し従って痔を起し、一かたならぬ苦しみをした上、とうとう鵠沼のお医者様にかかつてしまつた。腹の止り次第一刻も早く帰りたい。僕はもう尾籠ながらかき玉のやうな便をするのに心から底から飽きはててしまつた。菅忠雄君曰痔の痛みなんてわかりませんね。僕曰、たとえばくろがねの砦の上に赤い旗の立ってゐるような痛みだ。わかる?わからなければ度を」。 この痛みの表現、いかがでしょうか。 次のようなものもあります。「痔猛烈に再発、昨夜呻吟して眠られず。」、「痔痛みてたまらず、眠り薬を三包のみたれど、眠る事も出来かね、うんうん云ひて天明に及び候」 (本ホームページ内日記・書簡「芥川龍之介」もご参照ください) ○小説「歯車」から 「が、暫らく歩いてゐるうちに この歯車は、芥川自殺の約3か月前に執筆された最後の小説です。きっと死ぬまでこの病に苦しめられたのでしょう。 (本ホームページ内小説「歯車」もご参照ください) 参考・引用文献 「芥川龍之介全集」岩波書店、下島勲著「芥川龍之介の回想)近代作家研究叢書91 |
|||||