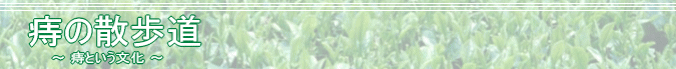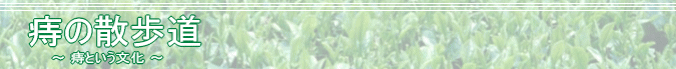■普救類方
「医者も多く薬屋で売薬が容易に入る都市部とは対照的に僻村の住民や貧しい庶民は、医薬に恵まれない暮らしを余儀なくされていました。
『普救類方』は、このような医療格差をすこしでも改善して民の苦しみを和らげようと、8代将軍徳川吉宗(1684―1751)が幕府の医官林良適(はやしりょうてき)と丹羽正伯(にわしょうはく)に命じて編纂させた書。幕府が所蔵する和漢の医書から、辺地の住民でも入手しやすい薬や療法を選び、庶民にも読解できるよう、漢文ではなく和文で記し、あわせて薬草図も載せています。全7巻。享保14年(1729)に完成した原稿を官費で出版し、値段を定め、江戸の本屋を通じて全国に販売させました。
林良適(1695-1731)は、享保7年(1722)に貧民のために設けられた小石川養生所で治療に当たった医師のひとり。丹羽正伯(1791-1756)は医者で本草学者。のちに吉宗の命で本草学の大著『庶物類纂』の編集に従事しました。」
国立公文書館 過去の展示会「病と医療」の中の『普救類方』解説ページから引用
■普救類方
次のとおり後陰之部(肛門、痔漏、脱肛)から一部を除き引用しています。
普救類方巻之二下
林 良 適
丹羽 正伯 纂輯
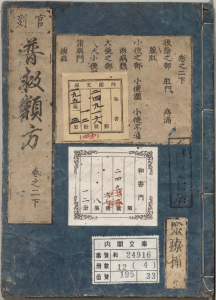 |
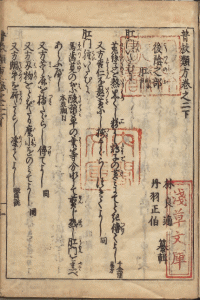 |
| 国立公文書館 デジタルアーカイブより転載 |
後陰之部
肛門
肛門いたむに
菟絲子を熬黒くし、粉にし、鶏子の黄みにてとき、
傅てよし 千金蘭易方
又方、杏仁熬黄にし、擣たゞらし、つけてよし 同
肛門腫いたむに
馬歯■(■は草かんむりに見)の葉、酸漿草の葉等分水にて煎じ、
熱し、肛門を熏べ
あらふべし 本草綱目
又方、■麻(■は草かんむりに、宀に丁)を搗たゞらし傅てよし 同
又方、刃物をとぎたる磨水をのみてよし 同
又方、蝸牛を研たゞらし、塗てよし 醫説
肛門の邊かたく腫、或はかゆく、痛たへがたきに
白礬三匁粉にし、熱き童便天目に二盃のうちへ入かきまぜ、 一日に
二度づゝ肛門をあらふべし 救急易方
又方、枳売をやき、其烟にて肛門を熏ぶべし、また枳穀を水に
煎じ 肛門を洗、并に粉にして飯のとり湯にて飲てよし 同
又方、杏仁を杵たゞらし付てよし、肛門の内虫ありて腫、
痒痛によし 本草綱目
肛門に瘡出来たるに
生漆をぬりてよし 同
又方、■茉(■は草かんむりに杏)の葉を搗たゞらし、絹につゝみ
肛門にさしこみ置べし日に三度とりかへてよし 同
又方、五倍子一匁、山椒子をさり炒て一匁、細辛焙りて
三分粉にし先葱湯にて瘡をあらひて後、右の粉薬を貼
てよし 同
又方、塩を熬、布につゝみ肛門を熨てよし、熱病にて虫を
生じ、肛門瘡出来たるによし 同
痔漏
一切の痔疾、或はいたみ。或はかゆきに
熊膽をぬりてよし 千金簡易方
又方、槐の根水にて煎じ、あらひてよし 同
又方、甘草を水にて煎じ、常に沃あらひてよし 衛生易簡方
又方、木綿の花と根とを擂、酒にいれのむべし、又木綿の花と
子とを水に煎じ、其湯烟にて痔をふすべて後あらふべし、或は
花と子とを焼、その烟にて痔を燻てよし 碎金方
(略)
痔はじめておこるに
馬歯■(■は草かんむりに見)を煮、熟し、しきりに食すべし、并に
湯にて痔を洗てよし此方を一月ほど用てよし 本草綱目
痔腫いたむに
ふるき橙子を焼、其烟にて痔をふすべてよし 同
又方、冬瓜を水にて煎じ、あらひてよし 同
又方、芥菜の葉を擣、餅のごとくにし、其上に肛門をあて 座してよし同
又方、枳穀を熱灰に入、うづみ焼にして熱して、痔を熨べし
、七八度ほど熨てよし 同
(略)
痔より常に血出るは、今はしり痔というなり
葱白根を水に煮、熟し、痔をふすべあらひてよし 本草綱目
又方、■魚(■は魚偏に皀卩)を煮て、つねに食すべし 同
又方、爵金の粉をぬりてよし 同
又方、槐木耳を粉にして一匁、飯のとり湯にて日に三度用て
よし 碎金方
(略)
出痔いたむに
槐花を水に煎じ、痔をあらひ并に少しづゝ飲べし 本草綱目
又方、五倍子をきざみ、水に煎じ、痔をあらひてよし 同
又方、蒲黄の粉一匁、温たる酒に入、空腹に飲てよし
本草綱目
又方、槐と柳を水に煎じ、痔をあらひて後出たる痔の上に
灸を七壮すへてよし 同
(略)
酒を多く飲により痔の出来たるに
絲瓜をやき、粉にして二匁、酒にて用ゆ 本草綱目
又方、黄連を酒にひたし、煮熟してほし、粉にして、酒糊にて豆の大に丸し
廿粒づゝ白湯にて用ゆ、酒痔血いづるに用てよし 同
痢病の後痔出たるに
冷水にて黄連の粉をとき、痔にぬりてよし 同
痔漏は痔久しく潰れ、孔あきて膿或は血など出るなり
亀肉に茴香と葱とをいれ、醤油にて煮常に食
すべし、用ゆうち酒醋等の熱なる物忌べし 同
又方、荊芥を水に煎じ、毎日あらふべし 同
又方、田螺一つの内へ龍脳一分いれ、田螺の水をかたぶけとり、先冬
瓜を水に煎じ、痔をあらひて後、右の水を傅てよし、
痔漏いたみつよきに用いてよし 同
又方、木饅頭の葉を焼、痔を薫てよし 傅信尤易方
(略)
脱肛
脱肛出ていらざるに
■魚(■は魚偏に皀卩)の頭を焼、粉にし、酒にて飲下すべし、
并に右の粉を生油にてとき、脱肛にぬりてよし 本草綱目
又方、胡■(■は草かんむりに妥)の子を擣、醋にて煮、布につゝみ
熨てよし、或は根を焼其烟にて薫てよし 同
又方、大なる田螺二つ三つとり、清き水に入、三四日程置泥を
はき出させ、黄連を粉にし、右の田螺の口へいれおけば、肉化けて
水となるなり、先濃煎じたる茶湯にて脱肛をあらひ、右の田螺
の汁を鳥の羽にひたし、脱肛にぬりて、其上に綿を付置べし 同
又方、蓮葉を焙、粉にして二匁づゝ、酒にて用ゆ、并に
蓮葉に右の粉を包、其上に脱肛をあて座してよし 同
(略)
脱肛あるひは脱腸とて、腸出ておさまらず、たとひ五六寸出て入がたき
にも蜂蜜一合、生姜汁一合よくかきまぜ、やわらかなる筆にて
浸、そろそろぬればおのづからおさまるべし 得効方
痢病の後脱肛出て入ざるに
冷水にて黄連の粉をときぬりてより 本草綱目
又方、蘿蔔を片、蜜にてひたし口に含み、汁を嚥べし、
味なきにいたりふたゝびかへて含むべし 同
又方、橡斗子を焼、粉にし、猪脂にときて、付てよし 同
又方、橡斗子殻を水に煎じ、あらひてよし 同
(略)
脱肛血出てやまざるに
桑木耳七匁、附子十匁粉にし、蜜にてねり、大豆の
大さに丸じて三四十粒、飯のとり湯にて用ゆ 本草綱目 附子の製法の所にあり
風熱にて脱肛出たるに
鐵粉白斂おなじく研、粉にして傅べし 同
大便出るごとに脱肛出るに
蝸牛をやき、灰にして、猪脂にてときつけてよし 同
小児脱肛出ていらざるに
蒲黄を猪脂にてとき、付けてよし 傅信尤易方
又方、菱角殻を影ぼしにし、水に煎じ、脱肛を薫洗ふ
べし、三五度あらふて後、麻油を肛門の四傍に塗てよし 砕金方
又方、伏龍肝五匁、■頭焼(■は上から口二つ、田、一、
黽)、灰にして二匁五分、百薬煎一匁三分粉にし、紫蘇を水にて濃
煎じたる汁にて用ゆ、小児の年数にした
がひて、薬を多く用てよし、并に右の粉薬を胡麻油にてねり、
脱肛につけてよし 得効方
小児腹ごゝろあしき時、大便のあとにて脱肛おさまらざるに
槐花を炒、粉にして、飯のとり湯にて用ゆ 同
又方、白龍骨を粉にし、付てよし、痢病の後脱肛出たるに用ゆ
衛生易簡方
科学書院「近世歴史資料集成 第Ⅱ期 第Ⅷ巻 民間治療(1)普救類方」浅見恵、安田健 訳編 一九九一年五月二十日初版第一刷 から引用
一部原文表記とは、異なります。
|