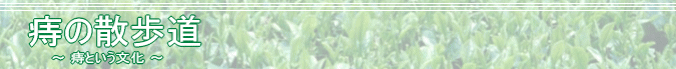
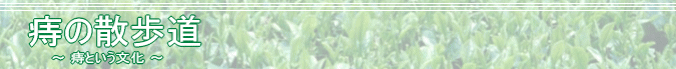
 ■ナポレオン■ 余の辞書に「痔」はある・・・ ■ナポレオン■ 余の辞書に「痔」はある・・・ 「歴史を変えた「痔」 ナポレオンの辞書に「不可能」はなかったが、「痔」はあった。 痔に悩んだ歴史上の人々の中で、世界的に最も有名な人物は、ナポレオン・ボナパルト(1769年~1821年)でしょう。ナポレオンは、偏頭痛、胃痛、排尿障害、疥癬など様々な疾患に罹っておりましたが、痔でもありました。この痔は、ナポレオンが28歳の時に初めて指摘されています。治療法としては、主にヒルに血を吸わせたり、特性のローションを使用していたと伝わっています。 フランス皇帝にまでなったナポレオンですが、結局1814年にエルバ島に流されます。しかし、翌年にはエルバ島を脱出し、ナポレオン最後の戦いとなったワーテルローでイギリスのウェリントンが指揮するヨーロッパ連合軍に敗れます。そして、この後、再びセントヘレナ島に幽閉され、そのまま51歳で死亡します。ちなみに、死因は、かつて砒素による毒殺説もありましたが、最近は、胃がん説が有力とのことです。 ところで、ワーテルローの戦いでは、ナポレオンに決定的な勝機がありながら、結果的に敗北しています。この敗北は、彼の痔の痛みと大いに関係があると言われ、フランス人にとって、今でも「ワーテルローの謎」とされています。 「フランス軍は六月十七日リニュイで緒戦に勝った。いつもならばナポレオンはこの勝利の勢いに間髪を入れず乗じたであろう。ところが、彼は痔の痛みでほとんど一晩中まんじりともできず、疲れ果ててやっと八時にのろのろ起き出した。彼は数時間にわたって何の命令も発せず、将軍たちを切歯扼腕させたが、その間連合軍は態勢を立て直すことができ、フランス軍の緒戦の勝利はふいになってしまった。その日一日中、ナポレオンはぼうっとして掴みどころがなく、決断力に欠けていた。その日の行動には、歴史家たちが理解に苦しむものがあった。ある時点で彼は馬から降りて、痛みのあまり顔を真青にして、垣根の杭にしがみついていた。そしてブリュッセルへ通じる道路傍で一時間も椅子にまたがったままでいた。ワーテルローは紙一重の差の勝利だった、と後年ウェリントン将軍は語っている。ナポレオンの疲労と激痛と、それによる行動力の制約が、この紙一重の差を生んだかもしれないのだ。」(A・カーレン「病気はヒトをどう変えたか」より) このようにナポレオンは、決定的なチャンスを逃し、運命の日に勝利を得ることができなかったのです。 歴史にifは禁物ですが、ナポレオンがもしその時痔の痛みがなかったら、もともと痔でなかったら、現在のような治療が可能であったなら、その後の世界の歴史は変わっていたかもしれません。 参考文献:倉田保雄著「ナポレオン・ミステリー」文春新書 フレデリック・F.カートライト著「歴史を変えた病」法政大学出版局 ネストール・ルハン著「天才と病気」日経BP社 A・カーレン著「病気はヒトをどう変えたか」秀潤社 ■加藤 清正■ トイレの長いのは・・・ 加藤清正といえば虎退治で有名ですが、この人のトイレが長いのも有名です。清正は痔がひどくトイレに入っているのは1時間にも及んだそうです。長いばかりでなく、下駄を履いて入ったそうで、しばしばトイレの中から家来に用を言いつけました。「清正が熊本在城のある夜、手洗に行くのに小姓二三人がつきそった。清正は不浄をきらって手洗では一尺ほどもある下駄をはいていたが、中でトントン踏みならした。小姓が近づいて用件を問うと、『いま急に思い出したことがある。庄林隼人を呼べ』と命じた。庄林隼人は風邪を引いて休んでいたが、急用だというので乱髪のまま登城すると、痔のわるい清正は、まだ手洗いの中にいた。」(安藤英男「加藤清正」から)清正は、一尺の下駄を履いて長時間しゃがみこみ、痔をさらに悪化させる悪循環に入ってしまいました。  ■松尾 芭蕉■ 旅に病んで・・・ 痔に病んで・・・ ■松尾 芭蕉■ 旅に病んで・・・ 痔に病んで・・・ 芭蕉の死は、元禄七年で時に五十一歳である。その死因については、毒茸を食べたことによるとされています。このとき辞世の句とされる「病中吟 旅に病んで夢は枯野をかけ廻る」を詠んでいます。 ところで、芭蕉には持病がありました。芭蕉はこの持病を、自ら「疝気」と「ぢ」と記しています。胆石(仙通)と痔疾と推定されるとのことです。芭蕉は、知人、門弟へ数多くの手紙を書いています(→日記・書簡「松尾芭蕉」)が、持病に関する記述がいくつかあります。持病は、在宅、旅行を問わず精神的に、体力的に、また風邪その他による心身の衰弱時にしばしば襲っていると考えられます。この「旅に病んで・・・」は、持病に加え、毒茸による発熱、下痢、腹痛時に詠んだものです。 (参考:大星光史著「文学に見る日本の医薬史」) 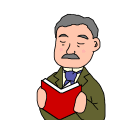 ■夏目 漱石■ 虫垂炎・腹膜炎、トラホーム、血痰(肺結核の疑い)、胃潰瘍、そううつ病、糖尿病そして痔・・・ ■夏目 漱石■ 虫垂炎・腹膜炎、トラホーム、血痰(肺結核の疑い)、胃潰瘍、そううつ病、糖尿病そして痔・・・ 夏目漱石の既往です。胃弱と神経衰弱が有名ですが、他にも疾患を持っていました。痔ろうにも悩みました。2回の手術も受けています。この痔疾患の経験は、漱石最後の小説で未完となった「明暗」に描かれています。この明暗は、主人公の痔の診察の場面からはじまり、入院、手術を背景として物語が展開します。(→小説「明暗」) また、漱石の書簡・日記にも多数の痔に関する記述があります。有名なところでは、「僕の手術は乃木大将の自殺と同じ位の苦しみあるものと御承知ありて崇高なる御同情を賜はり度候」と書かれた書簡があります(→日記・書簡「夏目漱石」)。痔に関してこのような句も詠んでいます。「秋風や屠(ほふ)られに行く牛の尻」、「切口の冷やかな風の厠より」。 ■マーラー■ サイクリングが最良の療法・・・ 1860年ボヘミアという辺境の地に生れたユダヤ人として、疎外感の中で一生を送った作曲家グスタフ・マーラーは、十二音技法などを先取りし、後期ロマン主義にあって近代音楽を導き、後世に大きな影響を与えました。その音楽には、素朴と単純さ、ロマン的な叙情性、深刻な絶望感、運命的な悲哀、また、最後の交響曲では、悲しみを克服した告別が表現されているといいます。(「作曲家別名曲解説ライブラリー① マーラー」から) このマーラーは、1895年の手紙で、自転車が届かないことを嘆きながら、(当時サイクリングは極めて人気のあるスポーツでした。)次のように書いています。「私の自転車はまだ影も形もありません!また昔からの持病(痔です)に悩んでいて、何をするにも不便なので、自転車が着かないのが特に打撃です。ハンブルグの経験からサイクリングが最良の療法だということはわかっているのです。」(「グスタフマーラー隠された手紙」中河原理訳から) 1901年、マーラーは痔が急激に悪化して、命にかかわるほどの出血、そして手術をしています。 「ブルックナーの『交響曲第五番』が演奏されたのは、一九〇一年二月二十四日の昼からの定期公演であったが、マチネーでヴェーバー、ドヴォルザーク、ブルックナーのプログラムを振ったマーラーは、その日の夜にも歌劇場で『魔笛』の指揮をしている。こうしたハードスケジュールで若い 同上の新潮文庫「マーラー」にある「G・マーラーの略年譜」から痔に関する箇所を引用します。 一八八八(28歳) 夏、ミュンヘンで手術(痔)を受ける。 一八九八(38歳) 痔の手術後ファールンで療養、夏に『子供の魔法の角笛』の二曲を完成。 一九〇一(41歳) 大出血のため手術(痔)を受ける(三月)。その後アパチーアで療養。 ヴィーン・フィルハーモニー管弦楽団を辞任、後任にヨーゼフ・ヘルメスベルガー・ジュニア(四月1日) 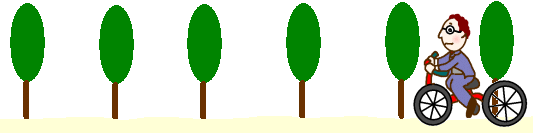 ■中村 勘三郎■ 痔のおかげで・・・ 「中支慰問から帰った翌昭和十九年一月、中村もしほ(勘三郎)にも水戸四十九連隊への召集令状が届く。そして、一月三十一日入営したが、入隊したその日に持病の痔のおかげで、即日帰郷を言い渡される。 「検査ではねられた気持はどうだ」と聞くので、「名残り惜しいであります」と答えたら、「ウソをつけ」と怒鳴られました。 営門を出て、水戸までついて来た石坂が泊まっているはずの温泉宿へ行くと、石坂はご機嫌で飲んでいて、「オッ、待ってやしたよ。マ、湯でもゆっくり入りやしょう」(勘三郎自伝「やっぱり役者」) (中村勘九郎他「中村屋三代記」から全文引用) 石坂:石坂高司、中村勘三郎の「番頭」  ■桂 米朝■ 毎日3席、6日間通す・・・持病悪化、応急処置で辛抱・・・痔は馬に乗るのが一番いい・・・ (略) カーッと口を開きまして、真っ赤な口ですな。 長いこと正座する商売で一種職業病でもある。私もずっと以前から さて明日以降どうするか。一万枚のチケットが売り切れ、まだ四日もある。今時、痔で死ぬこともあるまい、と腹を決めた。後で聞いたら、ホールの方では払い戻しに備えてお金を封筒に入れる作業にかかっていたという。 翌日からは一席しゃべって下りてくると、楽屋のふろに飛び込んで脱肛を押し込む。そして、しびれ薬のようなものをつけたガーゼを当て、ガムテープで固定して再びにこやかに舞台へ。こうしてお客さんに気付かれることなく、最終日の『二枚起請』『質屋蔵』などまで全席を終えることができた。 ラジオのレギュラー番組でこの話をしたら、親切なリスナーから様々な療法が寄せられた。地卵を五十個か百個絞ってとれる油を塗るときくとか、カンカン照りの日にその部分を直射日光に当てろとか、どこそこの神社のお札がいい。どうも決定打はなかったような気がする。 結局、踏ん切りがついて地元、尼崎市(兵庫県)の病院で手術した。先生が「見た目が悪くなるけどいいかな」というので、「見た目って、先生、あんなとこだれが見ますのや」 作家の三田純市さんが見舞いにきてくれた。「痔は馬に乗るのが一番いい」とまじめな顔でいう。「そんな話聞いたことがない。なんで馬なんや」といえば、「ほれ、『ジキル博士とハイド氏』ってあるやろ。ジィキルとハイドウ」。 (平成13年11月23日号、日本経済新聞「私の履歴書」から全文引用) ■赤瀬川 原平■ 痔核を自覚したとき・・・ (芥川賞作家で「老人力」などの著作で知られる赤瀬川氏は、22歳のとき十二指腸潰瘍で入院しました。赤瀬川氏がその退院後に家で療養していたときのことです。) 「(略) ごろごろしながら、どうも肛門がむず痒いのである。痒いとか痛いとか、そいういことは体のあちこちであるものだが、それがなかなか消えていかない。痛くはないのだけれど、そのむず痒さが時として痛さにまで接近するようで、何だろうかと思った。それまでの人生ではじめてのことである。 ぼくはわりあいと探究心のある方である。しかもまだちゃんと動けずに家でごろごろしている。よし、このむず痒さを探求してやろうと思って、ぼくは手鏡を持ってきた。それを畳の上にぺたんと置いてまたがって見た。 当然裸である。お尻が見える。考えてみたら自分の肛門を見るのははじめてである。 それはそうで、ふつうは見る必要がない。拭く必要はある。だいたい毎日一回、手にした紙を通して接しているけれど、それだけで一生を終える人がほとんどである。 (略) はじめて見るので、こんなものかと思うのだけど、自分の肛門の縁のところに、小指の先ほどのふくらみがぷつんとある。黒っぽいというか、グレーというかグレーはグレーでも、グレー光りのしたふくらみである。何だかそこにくっついたエイリアンみたいで、変な物が付いているぞ、と思った。 (略) それは痔の病の中でも痔核というものである。俗にいぼ痔という。俗にいうとあられもないですね。 とにかくそのようにして、ぼくは避けては通れないものとしての痔核を、自覚したのだった。 (略)」 (赤瀬川氏は、この後痔で悩みながら、6年後に手術をしています。) (講談社+α文庫「困った人体」赤瀬川原平著から全文引用、その後の経過についても詳しく記載されています。) ■杉田 玄白■ 江戸時代の最高の医学者の一人であった杉田玄白(1733年~1817年)も晩年には便秘、脱肛に悩みました。 「解体新書」を翻訳し近代医学への道を開き、また「蘭学事始」を著わした杉田玄白は、当時としては長寿である85歳の生涯を全うしました。ここでは、玄白の痔だけではなく、その養生法、晩年の人生観、健康状態、最後の心境などについて、少し断片的ですが記述します。 玄白69歳 (養生) 玄白は、古希の前年に、「子孫のため七不に因んで『養生七不可』を書き、 一、 昨日の非は恨悔すべからず。 一、 明日の是は慮念すべからず。 一、 飲と食とは度を過すべからず。 一、 正物に非(あらざ)れば荀(いや)しくも食すべからず。 一、 事なき時は薬を服すべからず。 一、 壮実を頼んで房(ぼう)を過すべからず。 一、 動作を勤めて安(やすし)を好むべからず。 こう戒めたあと、あとがきで生来病弱であった自分がこんにち健やかでいられるのは、病身が治ったのではなく、養生によるものであると語る。」(立川昭二著「江戸人の生と死」から引用) 玄白晩年 (九幸) 「晩年玄白は、『九幸』という号を常用していた。九つの幸とは、一に平和な世に生まれたこと、二に都で育ったこと、三に上下に交わったこと、四に長寿に恵まれたこと、五に俸禄を得ていること、六に貧乏をしなかったこと、七に名声を得たこと、八に子孫の多いこと、九に老いてなお壮健であること。これが、近世日本の最高の知識人といわれた人物が抱いていた人生観であった。」(立川昭二著同書から引用) 玄白84歳 ( 「一、 上の七 この 耄耋:「おいぼれ」のこと 竅(こう又はけつ):穴 下の二竅:肛門、陰茎 秘結:便秘 玄白85歳 (医事不如自然) 「医事不如自然(医事は自然に 八十五翁九幸老人書」 という絶筆を残し、文化14年(1817年)に輝かしい85年の生涯を閉じました。 |
|||||